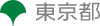- 実施概要
- 玉川大学の演劇スタジオや工房、音楽ホールで、小学生から中学生の子供たちが芸術に触れることができる5つのプログラムが行われました。
1. みんなでつくるなんでもワイルドパーク
「Dance×Light×Object(からだ×ひかり×もの)」
A【ダンスグループ】/B【照明グループ】/C【美術グループ】
2. Actor Training in English
3. 運動会で踊った「多喜雄のソーラン節」を唄って、和楽器で演奏して、みんなで表現しよう!
4. 「木のかわでかたちをつくってあそぼう」 ~間伐材で、森を手入れする大切さを伝えよう~
5. 自分だけの絵の具をつくって描いてみよう
玉川大学の自然あふれる広大なキャンパスの中で、子供たちが学びと表現を体験した1日の様子をご紹介します。
■取材日
8月10日(日)
■取材場所
玉川大学
プログラムレポート
プログラムレポート内容
オープンキャンパス
2025/10/08
キッズユースオープンキャンパス
~ワクワクが生まれるところ!玉川大学~
みんなでひとつのステージを作り上げよう!みんなでつくるなんでもワイルドパーク「Dance×Light×Object(からだ×ひかり×もの)」
ダンス、照明、美術の3グループに分かれて、合同で「ミニパフォーマンス」ステージをつくりあげます。玉川大学芸術学部ならではの横断的なワークショップで、最後は大学内にある本格的な演劇スタジオで発表します。
相手を感じながら身体を動かそう!
【ダンスグループ】講師:楠原竜也(芸術学部 演劇・舞踊学科 准教授)ほか
ペアになった子供たちが、楠原竜也先生のかけ声に合わせて、お互いの身体の一部をパッとくっつけるポーズをとっていきます。ただ身体の一部を合わせるだけではなく、しゃがんだまま、後ろを向いたままなど、「こんなのやってみる?」とお互いに声を掛け合いながら、意欲的に複雑なポーズに挑戦していきました。続いて、高学年の子供たちが一列に並んでさまざまな体勢でブリッジをつくり、低学年の子供たちがそれをくぐるという動きに挑戦。学生スタッフも全身を使ってエネルギッシュに子供たちをリードします。さらに、ペアで目線を合わせて動くアイコンタクトダンスに取り組む子供たちの集中力は、まるでプロのコンテンポラリーダンサーのよう。
「光の水族館」をつくろう!
【照明グループ】講師:赤羽佳奈(芸術学部 演劇・舞踊学科 講師)ほか
子供たちの席の前に置かれているのは、牛乳パックと虫眼鏡と工作キット。劇場に「光の水族館」をつくるために、赤羽佳奈先生がガイド動画を映しながら丁寧に手順を説明していきます。手順通りに自分で作業を進めていく子もいれば、それぞれのテーブルにいる学生スタッフに「これはどうするの?」と質問して、優しく教えてもらいながら頑張って進めていく子も。自分で描いた海の生き物のイラストがどんなふうに映し出されるのかを想像しながら、真剣に照明器具を完成させていく姿が見られました。いったい、どんな「光の水族館」が登場するのでしょうか?



小さなファッショニスタがたくさん!
【美術グループ】講師:長峰麻貴(芸術学部 演劇・舞踊学科 准教授)ほか
広大な土地に広がる玉川大学には丘と森もあります。美術グループが作るのは、そんな自然豊かな玉川の森に住む不思議な精霊になるための衣裳です。テーブルいっぱいに並べられた色とりどりの紙を使って、子供たちは個性豊かな帽子を作っていきます。キレイなお花をつける子、思いっきり高さのある帽子をつくる子と、それぞれが全く違うデザインの帽子を生み出していました。帽子が完成したら、今度は不織布を使ってマントを作っていきます。自分で作った衣裳を身に着けて、「縦に長くしてみたんだ」と誇らしそうに鏡で確認する姿は堂々たるもの。想像を超えるクリエイティブなファッショニスタたちに、長峰麻貴先生も「凄い!」と驚いていました。
いよいよ、3グループの成果が集結するパフォーマンス!
客席から保護者が見守る中、いよいよパフォーマンスがスタートしました。まずは照明グループが生み出す「光の水族館」がステージを幻想的に彩ります。青い海を泳ぐ大きなサメと、子供たちが作った照明器具から照射される色とりどりの海の生き物たち。続いて美術グループがカラフルな帽子やマントを身にまとってステージ中央に駆け出します。大きな三日月のオブジェの周りを軽快に飛びまわる姿は、さながら森の精霊たちのよう。
今度は、ダンスグループが元気いっぱいに飛び出してきました。学生スタッフのかけ声に合わせて、ワークショップで挑戦した“ブリッジくぐり”などを即興で次々に披露していく子供たち。全身から踊る喜びが溢れています。全員で再び「光の水族館」を眺めたら、今度はアイコンタクトダンスで盛り上げて、ポーズをします!最後は全員がステージ上に並んで、客席に向かって「ありがとうございました!」と元気に挨拶をして大盛況のうちにパフォーマンスは幕を閉じました。子供たちや学生スタッフの弾ける笑顔が輝いていました。



演技ってなんだろう?
「Actor Training in English」講師:アーカリ,ジェイスン(芸術学部 演劇・舞踊学科 教授)ほか
イギリスでパフォーミングアーツを学んだアーカリ,ジェイスン先生が演技の基礎を教えます。学生スタッフがフレンドリーに語りかけて、最初から和気あいあいとした一体感が生まれていました。演技のマインドトレーニングとして集中力・コミュニケーション力・想像力・観察力について先生が説明した後、それぞれの力を養うゲームやエクササイズを開始。まずは「気」のボールを使って、相手と目を合わせてから投げるというゲームで集中力とコミュニケーション力を高めます。最初は恥ずかしそうだった子供たちもどんどん積極的に動いていくように。
最後は二手にわかれて、「マネー(お金)」という曲にあわせて、ミニパフォーマンスを披露しました。学生スタッフが積極的に動き、子供たちも見よう見まねでダンス・パフォーマンスに取り組みました。「お金が大好きな人」になりきって身体を思いっきり動かしました。

可能性は無限大!
「『木のかわでかたちをつくってあそぼう』~間伐材で、森を手入れする大切さを伝えよう~」
講師:堀場絵吏(芸術学部 アート・デザイン学科 講師)ほか
堀場絵吏先生の指示のもと、「剥皮間伐」という手法で採集された樹皮を使って、クラフトボードに思い思いのモチーフを描いていきます。まずは樹皮をちぎったりサンドペーパーで磨いたりしながら、ハサミで切ることができる厚みにする作業からスタート。その後はチップを作り、クラフトボードに貼っていきます。子供たちはまるで一流の職人さんのように黙々と手を動かしていきました。出来上がった作品は、立体的でダイナミック!モチーフも猫や虫などの動物から、森の風景までバラエティに富んでいました。森を守るために木を切る必要があるという気付きから始まって、その間伐材を使って新たなもの(アート)を生み出し森の循環に貢献するという、学びの多いワークショップになりました。

自然のものから色を生み出す!
「自分だけの絵の具をつくって描いてみよう」
講師:児玉沙矢華(芸術学部 アート・デザイン学科 講師)ほか
玉川大学にある豊かな自然の素材を使って、自分だけの絵の具を作るワークショップです。児玉沙矢華先生の指示に従い、子供たちはまるで科学の実験室のような器具を使ってそれぞれの色を作っていきます。自然を感じるアースカラーから、ピンクやブルーなどカラフルな色まで、魔法のようにバラエティ豊かな色が生まれていきました。サポートする保護者の目も真剣です。学生スタッフの力も借りつつ、黙々と自分だけの色を生み出していく子供たちは立派な芸術家・科学者の風格を帯びていました。

みんなの頑張りにエールを!
「運動会で踊った『多喜雄のソーラン節』を唄って、和楽器で演奏して、みんなで表現しよう!」
講師:清水宏美(芸術学部 音楽学科 教授)、渡辺明子(芸術学部 音楽学科 教授)、小林史子(芸術学部 音楽学科 准教授)ほか
まずは各教室に分かれて唄・踊り・三味線・和太鼓の稽古をしてから、最後に全員がホールに集合してそれぞれの成果を披露していきます。グループごとのパフォーマンス後、学生スタッフや子供たち自身が感想を言い合い、「振り返り」を大切にした時間でした。「“どっこいしょどっこいしょ”のところで腰を低くすることにこだわりました」「みんなで合わせたときは心がひとつになった感じがしました」など、子供たちからは具体的な感想がたくさん出てきて、集中して練習に励んだ様子が伝わってきました。そして最後は、もちろん全員でソーラン節の演奏発表。和の精神を感じながら全力で行ったパフォーマンスは観る人たちを魅了しました。
学生たちの力で、どんどん個性と積極性を発揮していく子供たち
真剣に取り組み個性を発揮する子供たちや、徐々に積極的になっていく子供たちの姿に驚かされたと同時に、彼らをサポートする学生スタッフの生き生きとした姿も印象的でした。「多喜雄のソーラン節」を担当した清水宏美先生が「私一人ではとてもこのワークショックはできませんでした。学生たちは私の誇りです」と語るように、学生スタッフの「子供たちに伝えたい、教えてあげたい」という強い想いが子供たちにも伝わったからこそ、エネルギッシュで躍動感溢れるパフォーマンスや作品が生まれたのでしょう。
(取材・執筆:八巻綾)
ネククリの裏側
子供たちに寄り添い、プログラムを支えていた学生スタッフたち!
ダンスワークショップで先生からの「じゃあ、ペアをつくって!」という指示に、子供たちはもじもじするばかりでなかなか動くことができません。すると学生スタッフが、相手が見つからない子を見つけてペアを作ったり、自らその子のペアになったりと、すかさず動きます。弾ける笑顔のお姉さんたちに「ほら、こんなポーズはどう?」「すごい!それ面白い!」と積極的に声をかけられた子供たちの表情は、みるみるうちに好奇心とやる気に満ちていきます。今回のプログラムを通して、本格的な劇場やホールで実践的な学びを得られた子供たち。そんな子供たちの学びを支えていたのは、主体的で意欲的な学生スタッフたちでした。